はじめに
子どもの癇癪(かんしゃく)。
その瞬間のエネルギーに圧倒され、親もきょうだいも巻き込まれて、
一日の終わりには全員ぐったりしている…そんな日、ありませんか?
わが家にもそんな時期がありました。
でもあるとき、「癇癪が起きる前に気づく」という視点に出会ったことで、
ほんの少し、関わり方が変わりはじめたんです。
癇癪のきっかけは、意外とパターン化していた
わが家の息子は、感情が高ぶると癇癪を起こすことがあります。
とくに多いのが、「お姉ちゃんとの言い合い」から始まるパターン。
言い合いといっても些細なこと。
テレビの順番や、ちょっとした言葉の行き違い…。
でも、そこから一気にスイッチが入って、
声を張り上げたり、手が出たり、物を投げたり——。
最初は「またか…」「もうやめて」と思うばかりで、
とにかく“その場をおさめること”に必死でした。
「トリガー」に気づいたのは、療育の先生の一言から
ある日、通っていた療育の先生にこう聞かれました。
「何か“きっかけ”ってあると思う?」
最初はピンとこなかったのですが、少し考えてみて気づいたんです。
「夕方に多いな」「寝る前が多いな」
「登園後、いつもよりがんばった日は特に起きやすいかも」
つまり、“すでに疲れているとき”がトリガーになっているんだと。
声かけひとつで、本人も気づける
それから私は、子どもがちょっと不機嫌な顔をしはじめたときに、
先回りしてこう伝えるようになりました。
「今日はもうくたくただよね」
「疲れてると思うよ、がんばったね」
そうすると、息子も「うん…」と頷いたり、
「疲れてるのかも」と自分で口にしたりするようになってきたんです。
疲れている自分に気づけること、そしてそれを認めてもらえること。
それだけで、本人の安心感が全然違うように感じました。
このアプローチは、発達障害児の支援でも推奨されていて、
感情の言語化が苦手な子には、「今の状態を代弁してあげる」ことが有効とされています(※1)。
姉にも「お願い」をしてみたけど…
ただ、現実はそう簡単じゃありません。
たとえば姉弟げんか。
私はある日、お姉ちゃんにこうお願いしました。
「今日は疲れてるみたいだから、ケンカしないであげて〜」
すると返ってきたのは、
「私だって疲れてるんだけど!?」
——ほんと、そうだよね(笑)。
弟だけを守ろうとしていた自分に気づかされました。
それからは、「ケンカが始まりそうだな」と感じたら、
自分がすぐ間に入るようにしました。
料理中でも、皿洗い中でも、火を止めてでも動く。
そして「ふたりともそう思うよね」「どっちも悪くないよ」と、
どちらも否定しない言葉を意識するようにしました。
「先に気づいて動けた」日が、親の自信になる
そうした関わりを続けていると、少しずつ変化が出てきました。
もちろん、癇癪がゼロになるわけではありません。
でも、“今日のは防げたかも”と思える日が、明らかに増えてきたんです。
そしてその“ちょっとした予防の成功体験”が、
私自身の「やってよかった」という実感になっていきました。
おわりに
癇癪に困っているときは、つい「起きてから対応すること」に意識が向きがちです。
でも、“起きる前に気づく”という視点を持つことで、
子どもにも、親にも、やさしい時間が少しずつ増えていく。
もしあなたが今、同じように悩んでいるなら——
子どもの表情や行動の“前触れ”を、ちょっと意識してみてください。
きっとその中に、小さなサインが隠れているかもしれません。
✅参考文献
※1:国立特別支援教育総合研究所『発達障害のある子どもの感情調整支援』
(https://www.nise.go.jp/cms/)


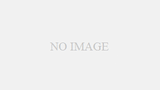
コメント