「もうどうしたらいいかわからない…」
発達障害のある子どもの癇癪(かんしゃく)に直面して、そう思ったことはありませんか?
我が家には、ADHDと自閉症スペクトラム障害の診断を受けた6歳の息子がいます。普段は元気で冷静さもあり、外から見れば「そんなに大変そうに見えない」と言われることもあります。
けれど、一度癇癪が起こると、まるで嵐のよう。自分自身や家族への暴力やに至ることもあり、そのたびに胸が締めつけられるような不安と疲労感に襲われます。
今回は、私自身が体験を通して見つけた「癇癪の対処法」を、いくつかの視点からご紹介します。
同じように悩んでいる方の心が、少しでも軽くなるきっかけになれば嬉しいです。
① 癇癪がひどい!対処の基本:まずは「自分の心」を冷静に保つべし
癇癪が始まると、親の心もかき乱されます。
「なんでまた…」
「どうしてうちだけ…」
「もう限界かもしれない」
そんな風に思ってしまうこともあるでしょう。でも、感情的になると、状況はさらに悪化してしまいます。
だからこそ、自分の心をいかに冷静に保てるかが、癇癪対策の第一歩になります。
▽ 心を落ち着けるための小さな工夫
- 深呼吸をする:腹式呼吸を意識して、ゆっくり吸って吐く。脳に酸素が届くことで、パニック状態を緩和できます。
- 外に出て空を見上げる:数十秒でもOK。空間を変えることで気持ちがリセットされやすくなります。
- 夫や信頼できる人に電話をかける:人と話すだけで、不安が軽減することがあります。ただ、愚痴ったり泣いたりしては逆効果。あくまで落ち着くために聞くのです。「少し声聞きたかった」「元気?」など重くならないよう心掛けます。
大切なのは、「自分が冷静でいられる方法」を知っておくこと。そしてそれを癇癪の最中でも実行する勇気です。
② 癇癪がひどい!対処法:時計をみて、終わりを予測する
癇癪がひどい時、「終わりの時間」を予測して心に余裕を持ちましょう。例えば我が息子の場合、癇癪のピークはだいたい50分ほど。最初は長く感じますが、「あと〇分」と終わりを見通せるだけで、気持ちに余裕ができます。
癇癪が始まったと感じたら、まずは時計を確認しましょう。
「よし、50分後には落ち着くはず」
そう思えるだけで、心が少し軽くなります。
③ 癇癪がひどい!対処法:鏡を見て、自分にエールを送る
言葉には、思っている以上に力があります。
脳は、耳から入った言葉を“事実”として処理する性質があるため、ポジティブな言葉が脳と心を落ち着けてくれるのです。
「私は怒らない。冷静でいる」
「頑張ってるよ」
「ちゃんと終わるから、大丈夫」
そういった言葉を、声に出して自分にかけてあげるのはとても効果的です。
④ 対処法:暴力・自傷行為には「静かに」「物理的に」向き合う
もしも子どもが物を投げたり、自分や他人を叩こうとする場合は、まず危険を物理的に取り除くことが最優先です。
- 壊れそうな物はサッと遠ざける
- 兄弟がいる場合は安全な場所へ誘導
- 投げそうな物を持つ前に、さりげなく手元から外す
ここで大切なのは、「ダメ!」「やめなさい!」などの否定的な言葉を使わないこと。
言葉にすると、親自身の感情も高ぶってしまい、火に油を注ぐことになりかねません。できるだけ無言で、淡々と対応しましょう。
▽「暴力の記憶」を作らせないことも大切
できる限り、「暴力をしてしまった」という事実を作らせないことを意識しています。
暴力行為は、本人にとっても強い自己否定に繋がるからです。
実際に我が家では、暴れ始めたらすぐに兄弟にスマホを渡して別室に避難してもらうこともあります。
「YouTube見てていいから、○○分まで待っててくれる?」とお願いして、安全を確保します。
⑤ 対処法:原因を「知る努力」をもって向き合う
癇癪が収まったら、できればその日の状況を振り返ってみましょう。
- 習い事や行事で疲れていた?
- 天気が悪くて一日中室内だった?
- 昼寝ができなかった?
- 動画の見すぎで興奮していた?
思い当たることがあれば、メモをして蓄積しておくと、次回へのヒントになります。
癇癪に理由がない日もあるのかもしれませんが、無理していることがあるのなら気づき、できない範囲を知ることはとても大事です。
⑥ 癇癪後の対処法:癇癪後は「わかってるよ」を伝える良きタイミング
癇癪のあと、子どもは意外と傷ついていたり、落ち込んでいたりします。
体も心もクタクタになっていることが多いです。
すぐに声をかけられなくても大丈夫。
少し落ち着いてきたなと感じたら、タイミングを見て、そっと伝えてみてください。
- 「今日は幼稚園がんばったね、えらかったよ」
- 「眠かったんだよね、たくさん遊んだもんね」
- 「大好きだよ、ぎゅーしようか」
障害の特性がある子どもたちにとって、「自分はちゃんと受け入れられている」と感じられることは、大きな安心につながります。
癇癪のあとこそ、その子なりの「しんどさ」をわかってあげようとする姿勢が、親子の信頼関係を少しずつ深めていく気がします。
まとめ|癇癪は「対応が勝負」、いつもじゃないから大丈夫
癇癪と向き合ってきた6年間。
今思うのは、「あのとき冷静でいられてよかったな」という小さな実感の積み重ねです。
少しずつ癇癪の頻度も減って、子どもから優しい言葉がぽろっと出てくると、じんわり嬉しくなります。
癇癪は、子どもの心の中のSOS。
うまく言葉にできない気持ちが、あふれてしまった形なのだと思います。
もちろん、親も大変。
うまくいかない日もあれば、「今日はちょっと無理だったな」と思う日もある。
それでも、なんとか向き合おうとしている自分のこと、少しだけでも認めてあげていいんじゃないでしょうか。
まずは、自分の心を落ち着けられる時間を、少しずつでも増やしていけたら。
そんなふうに思えたら、きっとそれで十分です。
ここまで読んでくださって、ありがとうございました。
この記事が、誰かの心にそっと届くものであったらうれしいです。
共感や体験など、よければコメント欄でシェアしてもらえたら励みになります。

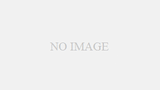
コメント